
FAQ
指導者・審判FAQ
サービス動作の前に、「ボールつき」をするとフォールトになるのですか?
サービスに関する競技規則の条項の中には「ボールつき」に関する規定は含まれていません。そのため選手が意図的にボール突きを何回も繰り返して、競技の遅延行為を行った場合を除き、この行為に対して主審がファウルもしくはフォールトを宣告することはできません。
(この判定基準は、過去から一度も変更された経緯はありません。)
また、選手がサービスエリアのチェンジ途中で、無意識にボールを床につくことはごく自然な行為であり、審判員がこの間に注視すべき対象行為ではありません。
仮に、競技規則で「ボールつき」を禁じた場合、主審はサーバーの動作を連続的に監視する必要が生じ、極端なことですがスコアの記入やレシーブサイドの確認ができないことになってしまいます。
主審のカウントコール後にボールつきをしたら、フォールト、またはファウル、あるいはウォーニングの対象になるのですか?
単なるボールつきなのか、サービスをしようとしてボールを放したのに打たなかったのか、これがフォールトの判断基準になります。
競技規則条文の「サービスをしようとして」とは、「サービスを打つためにトスをしようとして」ということであり、「サービスが開始される雰囲気の中で」ということではありません。つまり、単なるボールつきの場合は、「サービスをしようとして」には合致しません。
また、コールは、主審の進行上の指示ではありませんし、指示に従わない行為とは認められません。もちろんファウルもしくはウォーニングに相当するとは考えられません。
仮に規則を改定し、主審のコール後に限定してボール突きを禁じた場合においても、主審のコールのどの段階から適応するのかとか、声が小さくて聞こえなかった場合の対応とか、競技規則のより多くの条文追加と、審判員に対してより複雑な対応と判断が求められることになり、現実的ではありません。
サービス時の足の移動に関する規則を改定した目的は何ですか?
<改定前:~2016/03/31>
第15条 サービスの方法
(6) サーバーはサービスの開始から完了までは両足が床(地面)に接地し、移動してはならない。また、歩行、走行、跳躍など移動しながらの連続動作でサービスを開始してはならない。
<改定後:2016/04/01~>
第15条 サービスの方法
(6) サーバーは、歩行、走行、跳躍など移動しながらの連続動作でサービスを開始してはならない。サービスは、両足を床(地面)に接地した状態で開始し、完了までは、片足は必ず床(地面)に接地していなければならない。
改定した目的は、審判員の負担軽減と一般愛好者のサービス難易度の低減です。
審判法では、主審はサーバーの「打点の高さ」と「足の移動」の両方を判定することになっていますが、「打点の高さ」の判定が難しいうえに、「足の移動」が打球前か打球後かを判定しなければならず、主審の負担が大きいのが現状です。
また、誤審も多く、不信感を抱く選手もいます。
主審が判定するこの2点を比較すると、サービスの威力に大きな影響があるのは、「打点の高さ」です。
それに比べれば「足の移動」はあまり影響がありません。
そこで、主審が「打点の高さ」の判定に集中できる環境を整えるために、今回の改定となりました。
また、サービスを打つときに、体重を後から前に移動させながら打つことが多く、この体重移動はすべてのラケットスポーツの基本的な動きに合致します。
両足を固定させて打つようにすると、自然な身体の使い方が制限されるので、サービス成功率は低下し、特に初中級者にとっては難易度の高いショットといえます。
これまでにも、バウンドテニスの普及という観点ら、足の移動の制限を緩和するべきだという意見もありました。
「だれでもできる」生涯スポーツとしてのバウンドテニスの特色も考慮し、サービスの難易度を低減するために今回の改定となりました。
これまでは、足を床に着けたままズレると、足が移動したとして反則になりましたが、改定された規則ではどうなりますか?
手からボールを放して(サービスの開始)からラケットでボールを触れる(サービスの完了)までは、どちらか一方の足が床(地面)に着いていることが条件になります。
足が床(地面)に接地していれば、前後左右にズレたり、回転したりしても構いません。
以下に、有効な例を示しました。すべて右利きの場合で、図の太線が右手・右足です。
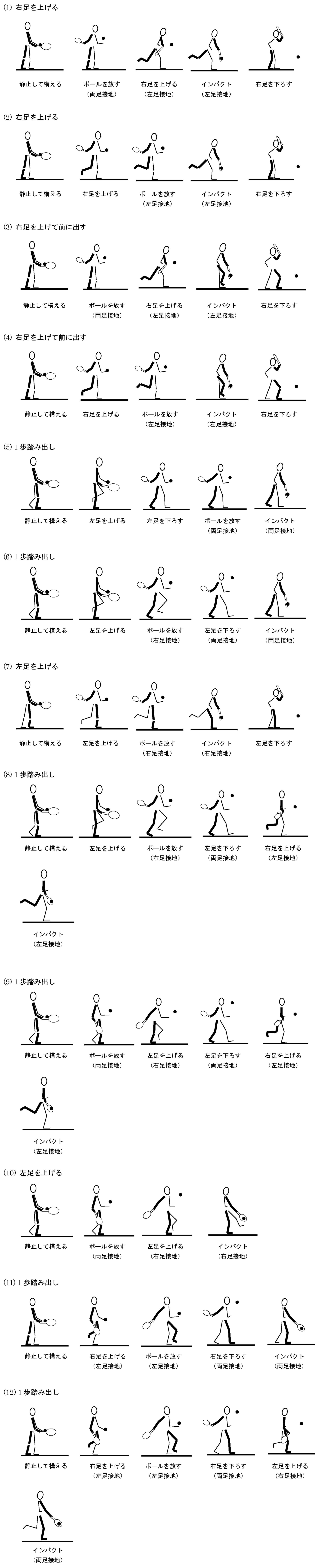
改定規則では、片方の足となっていますが、前足でも後ろ足でもよいのであれば、かえって主審を混乱させるのではありませんか?
主審は、サーバーが制止してサービスの構えをしてからボールを打つまでに、ジャンプして打っていないかどうかをチェックすればよいことになります。
規則では「歩行、走行、跳躍など移動しながらの連続動作でサービスを開始してはならない」となっていますが、前足を1歩踏み出して打つサービスは、歩行や走行による移動しながらの連続動作に該当するのではないでしょうか?
サービスの規則で禁止するのは、歩いたり、走ったり助走の勢いをつけてサービスをすること、およびジャンプして高い打点から打つことです。前足1歩だけの踏み出しは、歩行、走行には当たらず、助走の勢いを利用したことにはならないと解釈します。
また、サービス動作は後から前への体重移動が自然な動きになります。もっとも簡単な体重移動は1歩踏み出しです。したがって、初級者に対するサービスの指導面からも、1歩だけの踏み出しの動きは反則にしないことにしました。
ボールを放してから打つまでに片方の足だけが接地していれば良いのならば、トスでボールを高く上げ、打つまでに何歩も歩いても良いことになりませんか?歩くときにはどちらかの足が接地しているので。
今回の規則改定では、体重を後から前へ移動する動きは自然な動作であり、そのために、トスを上げるときに前足を1歩踏み出したり、インパクトで後ろ足が上がったりする動きを容認するのが主眼となっています。
したがって、構えの姿勢をとってからインパクトまでの間に何歩も歩く動きは反則となります。
「サービスは、両足を床に接地した状態で開始し」となっています。これまで、サービスの開始は「手からボールを放した瞬間」と教わってきましたが、それが変更になったわけですか?
サービスの開始は第15条(6)に書かれている「サービスをしようとして、ボールを手から放した瞬間」であり、変更されていません。
今回の改定では、サービス動作は、まず最初に、両足を接地して静止した構えの姿勢を取ることを示したものです。この構えの姿勢をした後に、ボールをトスすることによってサービスが開始となります。
初心者に初めてサービスを指導するときの注意点は何ですか?
初めてサービスをするときには、(1) 対角線の斜め半分のコートに入れること、(2) ベースラインの後で打つこと、(3) 腰の高さより下で打つこと、この3点を指導するとよいでしょう。
これまでは、足の移動について細かな注意点があったので、それを意識しすぎてサービスがぎこちない動作になることもありました。今回の改定により、足の移動ではなく、より本質的なラケットスイングに注意を集中して練習することができます。
フェアプレー精神とは、どういうことですか?
フェアプレーには大きく2つの意味があると考えます。
一つは、行動としてのフェアプレーです。
スポーツは定められたルールのもと、対戦相手と競い合い勝利を目指します。
その時に、ルールを守る、審判や対戦相手を尊重する、全力を尽くして戦い、勝っても奢らず、負けてもふてくされたりしないことなど、実際の行動としてのフェアなプレイです。
そしてもう一つは、フェアプレー精神というもの。
まさにフェアな心(魂)のことを意味します。これは、スポーツの場面に限らず日常生活の中でも、自分の考えや行動について善いことか悪いことかを自分の意思で決められること。自分自身の心に問いかけた時、恥ずかしくない判断ができる心(魂)のことをいいます。
この二つのフェアプレーは、スポーツを真に楽しむ上で欠かせないものなのです。
※公益財団法人日本体育協会
「フェアプレーで日本を元気に」皆様と共に推進するための趣意書より
フェアプレーに関して、規則に追加された条項は、どのような内容ですか?
平成25年4月1日に、競技規則第7条として施行された条項です。
内容については、PDF文書をご確認ください。
違反行為に対する罰則は、サッカーのように累積したり、次の試合に持ち越したりするのですか?
罰則の累積や持ち越しはありません。
その試合だけの罰則です。
だからと言って、各試合1度は反スポーツ的行為をしていいのかなどと考えてはいけません。
反スポーツ的行為とは競技規則に書いてある例だけですか?
それ以外は許されるのですか?
「してはいけないこと」を網羅することは不可能であり、規則では主な例を挙げているだけです。
フェアプレー精神に反する行為は全て対象になります。
なぜフェアプレーが必要なのですか?
バウンドテニスを皆が楽しくプレーするために必要なことです。
競技規則冒頭にその考え方(指針)が書かれています。
< はじめに>
バウンドテニスは、だれもが、生涯を通じて、楽しさや、喜びを味わうことのできるスポーツである。
このバウンドテニスの意義と価値を高めるために、プレーヤーは競技規則やアンチ・ドーピングに関する精神を遵守し、スポーツ規範に基づいて行動することが求められる。
試合中は、相手プレーヤーや審判員を尊重し、コートマナーを守り、フェアプレーに徹し、最善を尽くしてプレーしなければならない。
「警告」の前に「注意」があると聞きましたが、具体的にはどういうことですか?
「注意」という罰則はありません。
フェアプレー条項を浸透させるために、しばらくのあいだ、悪質でない微妙な行為の場合は、「警告(ウォーニング)」のまえに、主審が選手への教育的指導として、その行為が「警告」対象になる旨の「注意を与える」措置を取ろうということです。
「警告」など罰則のない試合が良い試合ですので、主審は、積極的に反則を取るのではなく、未然に防ぐよう努力しましょう。
今まで許されていた「コーチング」が禁止されたようですが、どうしてですか?
「コーチング」は、今までも許されていませんでした。
必携書に、「観客の守るべきマナー」として記載されています。
バウンドテニスをより楽しく素晴らしいものにするために必要なマナーであり、「ルールの前にマナーがある」ことは常識とされていました。
今回、競技規則改定により、ルールとして罰則が付いたということです。
フェアプレー条項は、全日本選手権大会など大きな大会だけのルールですか?
いいえ。
あくまで「競技規則」ですので、すべての試合に適用される「普通のルール」です。施行日は平成25年4月1日からです。
私(審判)はボールが「イン」だと判断して何も言いませんでしたが、選手はそのボールを打たず、「アウト」 と主張してきました。どうしたらいいでしょうか。
「あなたには “アウト” と見えたかもしれませんが、私は “イン” と判定しました。」 と言って、選手を納得させて下さい。
そのボールを打たなかった選手の失点です。
判定を下すのは、選手ではなく審判です。
私(審判)はボールが入っていないと思い、「アウト」とコールしました。そのコールを聞いた選手はボールを打ちませんでした。
ところが、副審が「今のボールは入っていました」と自信を持って言います。どのように判定したらいいでしょうか。
ボールが副審の近くに落下したのならば、副審の判定を受け入れて「レット」とします。
そのポイントは無効として、サービスからやり直します。
ボールがあなた(主審)の近くに落下し、自分の「アウト」の判定に自信があれば、判定通り に「アウト」とします。
どちらの場合でも、副審に再度確認し、選手にも改めてはっきりと最終判定を示すと良いでしょう。
指導者には、安全管理について責任があるといいますが、具体的なことを教えてください。
指導における安全管理についてリンクボタンから、下記について詳しく書いてあります。日ごろの指導に役立ててください。
バウンドテニス指導者保険制度導入の背景
スポーツの事故と法的責任について
安全配慮意識の徹底
子どもたちの練習会や大会への引率について、何か注意事項がありますか?
引率中の交通事故や、大会参加中の事故について、裁判になるケースがあり、主催者や引率者に厳しい判例になっています。
このような状況から、大会参加申込書などに、誓約書、同意書を添付させる競技団体が数多くなってきました。
ご参考までに、主な事項を挙げ、参考文例をリンクしますので、後でトラブルにならないようよく検討し、申込書などを作成してください。
参加に対する保護者の同意書
諸誓約事項
保護者への注意事項
個人情報の取り扱いについて
